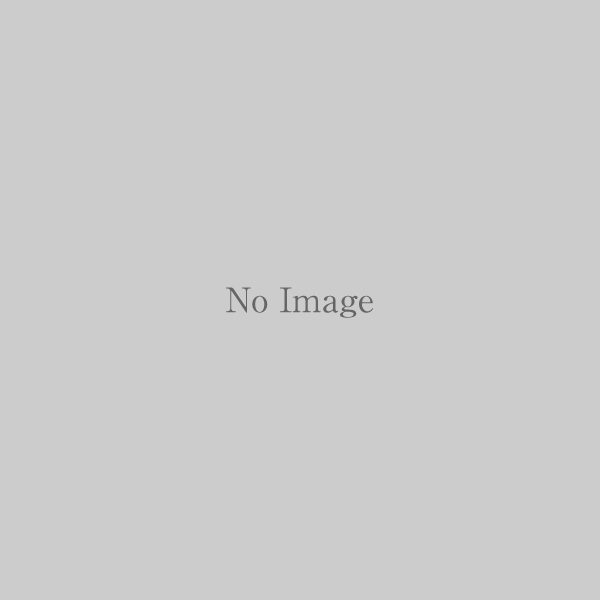平安時代末〜鎌倉時代初期
瀬戸窯の開始と灰釉陶器の生産
10世紀になると、猿投窯は知多半島、三河等の地域に窯場を拡散、北隣りの瀬戸にも10世紀後半から灰釉陶器を生産した窯が登場します。この時期の灰釉陶器は、近隣地域向けに生産されました。瀬戸でつくられた当時の灰釉陶器には、大小の椀をはじめ、さまざまな器種が見られるほか、緑釉陶器の素地も出土しており、その生産への関与がうかがわれます。しかし、11世紀中頃になると、量産化に伴う形の簡素化・粗雑化が進み、限られた器種を主体とする生産に移行します。
 灰釉縄手付瓶
灰釉縄手付瓶
11世紀中期/広久手F窯出土